巷に溢れるさまざまな腸活情報。あなたが実践している腸活アクションは、本当に正しい腸活になっている!? 京都府立医科大学の内藤裕二教授に伺います。
「“理想的な腸”は、わかりやすい自覚症状がありません。つまり、この状態だったらいい、悪いという判断が難しいので、1つの指針として“腸年齢”のお話しをしました。“理想の腸”の判断も難しいぐらいですから、実は腸活も世の中には正しいもの正しくないもの、更には科学的データがとれていないもの、たくさんの情報が溢れています。理想的な腸は、多様な腸内細菌がいる状態。腸活とは、腸内細菌の質と量を担保するために食生活やその他で改善していくことです。正しい知識を身につけて、賢く腸活を進めていきましょう!」(内藤先生)
この腸活、正しい?ウソ・ホント?
①「とにかく腸に良い食材を食べれば腸活になる」
答え:△(一部は正しいが、それだけでは不十分)
確かに、食物繊維・発酵食品・オメガ3系脂肪酸・オリゴ糖などは、有用菌(善玉菌)を増やして腸内環境を整えます。しかし、悪玉菌のエサになる動物性たんぱく質、糖質、塩分、脂質、アルコールを摂りすぎると、腸活の効果が薄れてしまうのです。
✅ 腸活のポイント
・ 有用菌を増やす食品を摂る(発酵食品・食物繊維・オメガ3系脂肪酸)
・ 悪玉菌を増やす食品を控える(脂肪・糖分・塩分・アルコールの摂りすぎに注意)
「良いものを食べるだけ」ではなく、「悪いものを控える」ことも腸活には不可欠です。
②「朝食は食べなくても腸活には影響しない」
答え:×(影響あり!)
朝食を摂ることは、腸の健康にとって非常に重要です。腸の蠕動運動は自律神経によってコントロールされており、便秘を防ぐためにも規則正しい生活で自律神経を整えることが大切です。
人間の体内時計は、地球の24時間サイクルよりも少し長く、約24時間30分とされています。そのままでは毎日少しずつズレが生じてしまうため、朝に体をリセットし、地球のリズムに合わせることが必要になります。
体内時計を整えるには、「親時計」と「子時計」の2つのリセットが欠かせません。
・親時計のリセット → 朝、太陽の光を浴びることで整う
・子時計のリセット → 朝食(特に炭水化物)を摂ることで整う
朝食を摂ることで、胃が刺激を受け、その信号が腸に伝わることで腸の蠕動運動が活発になります。その結果、スムーズな排便を促し、腸内環境が改善されるのです。
また、体内時計が正常にリセットされると、1日の活動リズムが整い、自律神経のバランスも安定します。そのため、腸活だけでなく、集中力やパフォーマンスの向上、労働生産性の向上にもつながるのです。
朝食は単なる食事ではなく、腸と体のスイッチを入れる大切な役割を担っています。腸の健康を保つためにも、朝食をしっかり摂る習慣を身につけましょう。
③「乳酸菌は摂れば摂るほど腸活に良い」
答え:〇(基本的に問題なし)
乳酸菌は、アレルギーや免疫機能に影響を及ぼす細菌であり、生きたまま腸に届いても、死滅した状態で届いても効果があるとされています。腸内にはすでに乳酸菌が常在していますが、ヨーグルト・乳酸菌飲料・漬物などの発酵食品を摂取することで、腸内環境の維持や改善に役立ちます。
市販のヨーグルトやサプリメントでは「乳酸菌400億個配合」などと表示されることがありますが、腸内には約1兆個以上の腸内細菌が存在しており、その数と比較すると乳酸菌の摂取量はわずかです。そのため、摂れば摂るほど劇的に効果が上がるわけではありませんが、日常的に摂ることが推奨されます。
ただし、日本人の食生活では乳酸菌よりも食物繊維が不足していることが問題視されています。腸内の善玉菌(有用菌)のエサとなる食物繊維が十分でなければ、乳酸菌の定着も難しくなります。乳酸菌を意識して摂るとともに、まずは食物繊維の摂取量を増やすことを心がけることが、より効果的な腸活につながります。
④「腸活には、まずサプリメントを取り入れるのがベスト」
答え:△(基本は食事から!)
サプリメントは腸活の補助にはなりますが、まずは普段の食生活を見直し、食事から有用菌を摂ることが最優先。サプリメントは「プラスアルファ」として取り入れ、短鎖脂肪酸などの腸に良い成分を補う形が理想です。
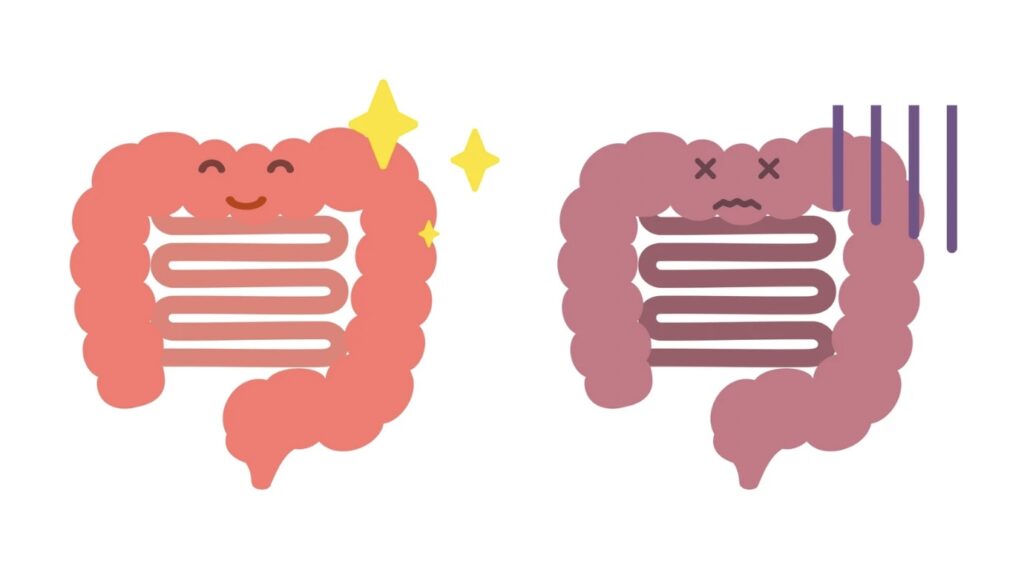
⑤「玄米は白米よりも腸活に良い」
答え:〇(玄米のほうが食物繊維は豊富!)
日本人の食事で最も不足している栄養素のひとつが食物繊維。食物繊維は、腸内環境を整え、有用菌を増やす役割があります。白米と比べて玄米には食物繊維やミネラルが豊富に含まれているため、腸活には玄米のほうが適しています。
⑥「小麦粉を抜いた食生活は腸活になる」
答え:×(小麦アレルギーの話で、腸活とは別問題)
最近、小麦を避ける食生活が流行していますが、小麦が腸に悪いわけではなく、アレルギーの有無が関係します。
✅ 小麦アレルギーのある人 → 小麦を控えると腸の調子が改善する可能性あり
✅ アレルギーのない人 → 小麦を抜いても腸活には特に影響なし
小麦を避ける前に、アレルギー検査を受けることが大切です。
⑦「食事制限やファスティング(断食)は腸活に良い」
答え:×(むしろ逆効果になることも!)
私は腸活においてはあまりおすすめできません。腸は、食べ物が腸を通ることで活性化する臓器です。腸管の中から栄養を摂っているので、絶食は腸にとってよくない行為と考えています。ファスティングをすると、やり始めの3カ月ぐらいは免疫を維持できるなどいい効果が期待できると科学的なデータもでているのですが、2年など長く続けていると腸の老化が加速していってしまいます。ファスティングをするなら、工夫して実行しないと腸活には悪影響をおよぼしてしまうリスクがあります。
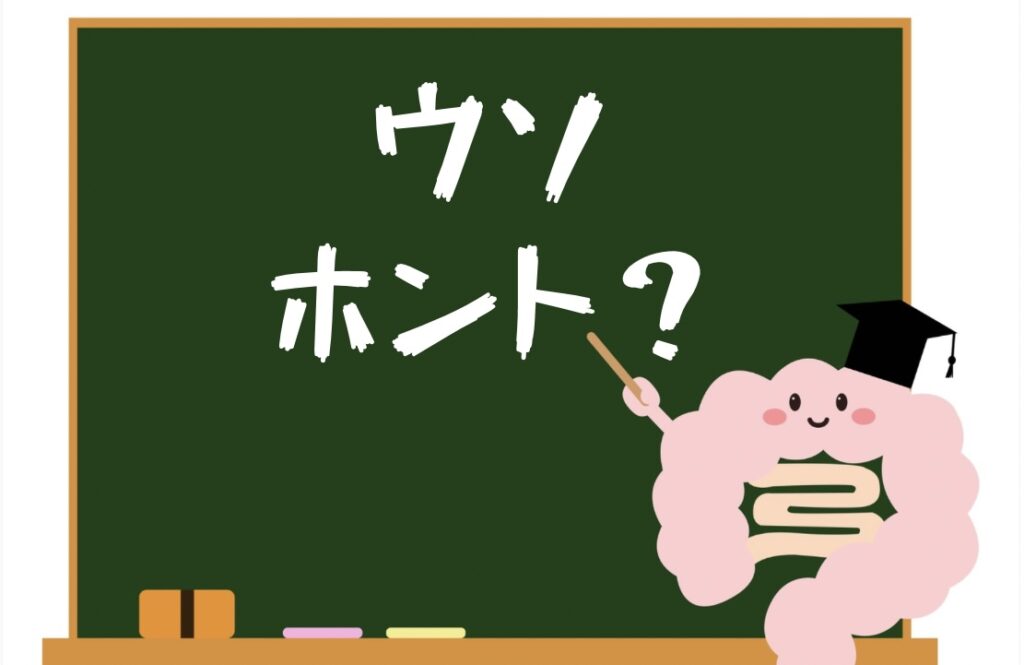
⑧お腹が柔らかいほうが、いい腸
答え:△(蠕動運動を促す効果はあり)
お腹の柔らかさや硬さだけで腸の状態を判断するのは難しいですが、腸もみをすることで蠕動運動を促す効果が期待できます。入浴時など、体を温めながら「の」の字を描くように優しくお腹をマッサージすると良いでしょう。
⑨姿勢を正すことは腸活に有効
答え:△(体を動かすほうが大事)
姿勢を正すこと自体よりも、日常の身体活動を増やすことが大事。座りっぱなしの時間が長いと腸の働きが低下するため、エスカレーターではなく階段を使う、電車では座らずに立つ、長時間座るときはバランスボールを活用するなど、意識して体を動かしましょう。
⑩「楽しく会話することが腸活に良い」
答え:〇(腸と脳は密接に関係!)
人は孤独になると、脳の指令によって小腸の機能が低下し、腸内細菌をコントロールする細胞の生成が減少し、腸内環境が悪化することが分かっています。さらに、腸内環境が悪くなると、逆に腸から脳へ悪影響を及ぼす信号が送られ、「腸脳相関」の悪循環に陥ってしまいます。
脳の状態を改善するだけで腸内環境が確実に良くなるわけではありませんが、社会とのコミュニケーションを増やしたり、楽しい話題を考えたり、ポジティブな想像をすることが腸に良い影響を与えることが分かっています。
人間の腸内細菌は、生まれたときはゼロの状態で、3〜5歳までにさまざまな腸内細菌を取り込み、多様化していきます。しかし、大人になってからは他者と話すことで腸内細菌をもらい、定着させることはできません。そのため、「誰かと会うことで腸内細菌が増える」という意味では腸活にはなりませんが、会話を楽しむことで腸に間接的な良い影響を与えることは間違いありません。
まとめ
腸活には多くの情報があり、正しいものもあれば誤ったものもあります。科学的根拠に基づいた正しい腸活を行うことが、健康な未来への第一歩です。
今日から「本当に腸に良いこと」を意識し、5年後、10年後も健康で元気に過ごせる腸を育てていきましょう!
今回教えてくれたのは…
-
京都府立医科大学大学院 生体免疫栄養学教授 : 内藤裕二さん
消化器専門医として最新医学に精通し各地で講演も行っている。消化器病学や消化器内視鏡学、生活習慣病の他、健康長寿や抗加齢医学、腸内フローラや酪酸菌研究も専門としており、「京丹後長寿コホート研究」で腸内フローラ解析に携わっている。酪酸菌と健康長寿の関係などの研究をはじめ、長年腸内細菌を研究し続けている本領域の第一人者。
記事をシェア